日本酒は米を主原料にして造られる醸造酒である。
よって、用いる米によって酒の味も大きく変わる。
酒造りに向くように開発された米を「酒造好適米」または「酒米」と呼ぶ。
種類は数多くあり、作り手は、めざす味に合わせて米の種類を選んでいくのである。
酒造好適米は一般的な食用米とは異なり、特に日本酒の製造に適した特性を持っています。
以下に、その主な特性をいくつか挙げてみます:
- 大粒:酒造好適米は食用米と比べて粒が大きいです。これは、米の中心部にある「白心」が大きく取れ、そこに麹菌を繁殖させることができるからです。白心部分は精米すると露出しやすく、酒造りにおける発酵の元となる糖分を生み出すのに重要な役割を果たします。
- タンパク質の少なさ:酒造好適米は、食用米と比べてタンパク質の含有量が少ないです。タンパク質が多すぎると日本酒の味が荒くなったり、雑味が出たりするため、酒造りにはタンパク質の少ない米が適しています。
- 粘り気の少なさ:酒造好適米は、食用米と比べて粘り気が少ないです。これは、酒造りでは米がパラパラとしていて、水分と空気を均一に吸収しやすい方が、酵母と麹菌の働きを促進し、良質な日本酒を生み出すことに寄与します。
日本には多くの酒造好適米があり、それぞれの品種が持つ特性は異なり、それが日本酒の多様な味わいを生み出す一因となっています。
各地で新たな酒造好適米の開発が日々行なわれており、作り手もそれぞれ性質を活かしながら多様な味を造り出している。
主な酒造好適米10種それぞれの特徴をご紹介していこう。
山田錦(やまだにしき)
酒米の王者といわれる。大粒で、高精米に向く。兵庫県農事試験場が開発。昭和11年登録。母は「山田種」、父は「短稈渡船(たんかんわたりぶね)」。長らく、「山田錦」を使わなければ、全国新酒鑑評会の金賞は取れない、とまでいわれていた。
「山田錦」は日本酒の製造に用いられる酒米の中でも特に名高い品種で、特に高級酒である純米大吟醸酒の製造によく使われます。その特徴は以下の通りです:
- 大粒:山田錦は粒が大きいため、精米しても白心(しんぶ)が残りやすいです。白心は麹菌にとって最適な栄養源で、これが多いほど良質な日本酒ができます。
- タンパク質とアミロースの含有量:山田錦はタンパク質とアミロース(でんぷんの一種)が多く含まれています。これにより、山田錦から作られた日本酒は深みとコクがあり、また華やかな香りが特徴となります。
- 栽培が難しい:山田錦は病気に弱く、また日照時間や水質にも敏感であるため、栽培が難しいとされています。そのため、山田錦を使用した日本酒は高価なものが多いです。
山田錦は特に兵庫県で栽培されることが多く、特に「特A地区」(最も品質が高いとされる地域)で栽培された山田錦は最高品質とされています。この地区で栽培された山田錦を使った日本酒は、その品質と希少性から高級酒とされ、日本国内外で高い評価を受けています。
雄町(おまち)
「雄町(おまち)」は、山田錦と並ぶ日本酒の酒造りに適した酒米の一つで、特に岡山県での栽培が有名です。以下にその特性を述べます:
- 大粒:雄町もまた山田錦同様、粒が大きい特性を持っています。これにより、精米しても白心が残りやすく、発酵の元となる糖分を豊富に生み出すことができます。
- 味わいと香り:雄町から造られる日本酒は、深みとコクがあり、まろやかで上品な味わいが特徴とされます。また、独特の香りを持つため、特に香りを重視する酒造りに適しています。
- 栽培の難易度:雄町もまた、山田錦同様に病害に弱く、栽培が難しいとされています。これは、栽培に手間とコストがかかる一方で、その品質から高級酒の原料として重宝されています。
- 歴史:雄町は古い品種で、江戸時代から存在していたとされています。そのため、日本酒の歴史や文化に深く根ざしています。
雄町を使用した日本酒は、その独特の特性から多くの酒造り師たちに愛され、さまざまな表現の日本酒を生み出しています。また、特に岡山県の雄町は「真田雄町」とも呼ばれ、日本酒造りにおいて非常に高い評価を得ています。
五百万石(ごひゃくまんごく)
昭和32年に、新潟県農業試験場で開発された米だ。母は「菊水」、父は「新200号」。
「五百万石(ごひゃくまんごく)」は、日本で最も生産量が多い酒造好適米の一つで、特に福井県を中心に栽培されています。その特性は以下の通りです:
- 中粒:五百万石は中粒種で、山田錦や雄町と比較すると粒はやや小さいです。しかし、粒が均一で割れにくい特性があります。
- 味わいと香り:五百万石から作られる日本酒は、軽快でスッキリとした味わいと、爽やかな香りが特徴です。特に辛口の酒を得意とし、口当たりが良く飲みやすいため、多くの人々から支持されています。
- 栽培の容易さ:五百万石は病害に強く、栽培が比較的容易です。また、大量に収穫できるため、生産量が非常に多く、広範囲で栽培されています。
- 利用範囲:五百万石は、その特性から幅広いタイプの日本酒の製造に使用されます。特に、本醸造酒や吟醸酒に多く用いられます。
五百万石を使用した日本酒は、その飲みやすさから幅広い層から支持を受けており、特に福井県の地酒として多くの銘柄が存在します。また、その特性から様々な表現の日本酒を生み出すことができ、多様な日本酒の世界を楽しむことができます。
亀の尾(かめのお)
明治26年、山形の篤農家、阿部亀治が冷害で生き残った稲を選抜改良。
「亀の尾(かめのお)」は、山田錦や雄町と並ぶ、日本酒の製造に使用される高級酒米の一つで、特に福井県での栽培が有名です。以下にその特性を述べます:
- 大粒:亀の尾は大粒種で、山田錦や雄町と同じく精米に適した大きさを持っています。この大きさが発酵に必要な糖分を豊富に生み出すことを可能にします。
- 味わいと香り:亀の尾から作られる日本酒は、深みとまろやかさを兼ね備え、また華やかな香りが特徴です。これらの特性は特に純米大吟醸酒などの高級酒の製造に適しています。
- 栽培の難易度:亀の尾は病害に弱く、特に稲作病害である穂いもち病に対する抵抗力が低いため、栽培が難しいとされています。しかし、その困難さを乗り越えた酒米からは、非常に質の高い日本酒が生まれます。
- 歴史:亀の尾は古い品種で、日本酒の歴史や文化に深く根ざしています。また、その名前は稲穂の形状が亀の尾に似ていることから名付けられました。
亀の尾を使用した日本酒は、その品質から非常に高い評価を受けており、特に福井県の地酒として知られています。また、その独特の特性から多様な表現の日本酒を生み出すことが可能で、日本酒の豊かな世界を体験することができます。
美山錦(みやまにしき)
昭和53年、長野県農業試験場で生まれた。「たかね錦」へのガンマ線照射により突然変異した米。ちなみに「たかね錦」の母は、「北陸12号」、父は「東北25号」である。繊細な香りを持つ、軽い味の酒に仕上がるという。
「美山錦(みやまにしき)」は、日本酒の製造に使用される酒造好適米の一つで、特に京都府での栽培が有名です。以下にその特性を述べます:
- 中粒~大粒:美山錦は中粒種から大粒種に分類され、精米に適した大きさを持っています。この大きさが発酵に必要な糖分を豊富に生み出すことを可能にします。
- 味わいと香り:美山錦から作られる日本酒は、深みとまろやかさを兼ね備え、また独特のフルーティな香りが特徴です。これらの特性は特に純米酒や吟醸酒の製造に適しています。
- 栽培の難易度:美山錦は病害に弱いとされており、特に穂いもち病に対する抵抗力が低いため、栽培が難しいとされています。しかし、その困難さを乗り越えた酒米からは、非常に質の高い日本酒が生まれます。
- 地元との結びつき:美山錦は、京都府の地域特性に合わせて開発された酒米で、その地元である京都府の地酒として多くの銘柄が存在します。
美山錦を使用した日本酒は、その品質から非常に高い評価を受けており、特に京都府の地酒として知られています。また、その独特の特性から多様な表現の日本酒を生み出すことが可能で、日本酒の豊かな世界を体験することができます。
八反錦(はったんにしき)
八反の名を持つ米は、広島でいくつも開発、栽培されている。在来品種「八反草」を改良した「八反35号」と、飯米の「秋津穂」を掛け合わせて生まれたのが「八反錦」である。キレよく、香りの爽やかな酒になるという。
以下にその特性を述べます:
- 大粒:八反錦は大粒種で、精米に適した大きさを持っています。この大きさが発酵に必要な糖分を豊富に生み出すことを可能にします。
- 味わいと香り:八反錦から作られる日本酒は、深い味わいと豊かな旨味、そして独特の香りが特徴です。これらの特性は特に純米酒や吟醸酒の製造に適しています。
- 栽培の難易度:八反錦は病害に弱いとされており、特に穂いもち病に対する抵抗力が低いため、栽培が難しいとされています。しかし、その困難さを乗り越えた酒米からは、非常に質の高い日本酒が生まれます。
- 地元との結びつき:八反錦は、広島県の地域特性に合わせて開発された酒米で、その地元である広島県の地酒として多くの銘柄が存在します。
八反錦を使用した日本酒は、その品質から非常に高い評価を受けており、特に広島県の地酒として知られています。また、その独特の特性から多様な表現の日本酒を生み出すことが可能で、日本酒の豊かな世界を体験することができます。
愛山(あいやま)
かつては兵庫県の老舗蔵でのみ使われていたが、『十四代』を醸す山形の高木酒造がこれを用いることで、甘みのあるその味が広く世に知られるようになった。昭和16年、兵庫県立明あか石し 農業改良実験所で、「愛船117」と「山雄 67」から生まれた。
高木酒造は今も「愛山」を得意とする蔵のひとつ。用いると甘みとコクが生まれるという。
以下にその特性を述べます:
- 大粒:愛山は大粒種で、精米に適した大きさを持っています。この大きさが発酵に必要な糖分を豊富に生み出すことを可能にします。
- 味わいと香り:愛山から作られる日本酒は、深い味わいと豊かな旨味、そして独特の香りが特徴です。これらの特性は特に純米酒や吟醸酒の製造に適しています。
- 栽培の難易度:愛山は病害に弱いとされており、特に穂いもち病に対する抵抗力が低いため、栽培が難しいとされています。しかし、その困難さを乗り越えた酒米からは、非常に質の高い日本酒が生まれます。
- 地元との結びつき:愛山は、新潟県の地域特性に合わせて開発された酒米で、その地元である新潟県の地酒として多くの銘柄が存在します。
愛山を使用した日本酒は、その品質から非常に高い評価を受けており、特に新潟県の地酒として知られています。また、その独特の特性から多様な表現の日本酒を生み出すことが可能で、日本酒の豊かな世界を体験することができます。
千本錦(せんぼんにしき)
平成14年に登録された比較的新しい酒米。広島で「中生新千本(なかてしんせんぼん)」と、「山田錦」を交配し、生み出された。穂はやや長く、粒は大きめ。硬めで、醸造に少し時間がかかるが、その分、酒質は美しくなる傾向があるという。
以下にその特性を述べます:
- 大粒:千本錦は大粒種で、精米に適した大きさを持っています。この大きさが発酵に必要な糖分を豊富に生み出すことを可能にします。
- 味わいと香り:千本錦から作られる日本酒は、深い味わいと豊かな旨味、そして独特の香りが特徴です。これらの特性は特に純米酒や吟醸酒の製造に適しています。
- 栽培の難易度:千本錦は病害に弱いとされており、特に穂いもち病に対する抵抗力が低いため、栽培が難しいとされています。しかし、その困難さを乗り越えた酒米からは、非常に質の高い日本酒が生まれます。
- 地元との結びつき:千本錦は、京都府の地域特性に合わせて開発された酒米で、その地元である京都府の地酒として多くの銘柄が存在します。
千本錦を使用した日本酒は、その品質から非常に高い評価を受けており、特に京都府の地酒として知られています。また、その独特の特性から多様な表現の日本酒を生み出すことが可能で、日本酒の豊かな世界を体験することができます。
白鶴錦(はくつるにしき)
白鶴酒造が開発した酒米。平成19年に登録された。母は「山田穂」、父は「渡船」で、「山田錦」の近縁品種であるが、穂数の多寡や芒(のぎ)などに明確な違いがある。最近は『十四代』にも白鶴錦を使った商品がある。
酒未来(さけみらい)
高木酒造が開発。育成年は、平成11年。母は「山酒4号」、父は「美山錦」。優雅で瑞々しい酒の味に仕上がり、現在では20以上の気鋭蔵が用いる。父母を入れ替えて生まれた、「龍の落とし子」という品種もある。
「酒未来(さけみらい)」は、新たな酒造好適米の一つで、その名前は「日本酒の未来を切り開く」という願いが込められています。
酒未来は、福井県で開発された新品種で、その特徴は次の通りです:
- 耐病性:酒未来は、いもち病に対する耐性が非常に高いとされています。この耐病性は、農家にとって大きな利点となり、より安定した酒米の生産を可能にします。
- 米の大きさ:酒未来は、大粒種であり、その米粒は山田錦や五百万石と比較しても大きいとされています。この大きさは、酒造りにおいて有利であり、より多くの糖分を発酵させることができます。
- 味わい:酒未来から作られる日本酒は、フルーティな香りと、きれいな甘み、そして深い旨味が特徴とされています。
酒未来は、新たな酒造好適米として期待されており、その特性を活かした多くの新しい日本酒が作られています。また、その耐病性と大粒さは、日本の酒造りの未来を明るく照らす要素となっています。
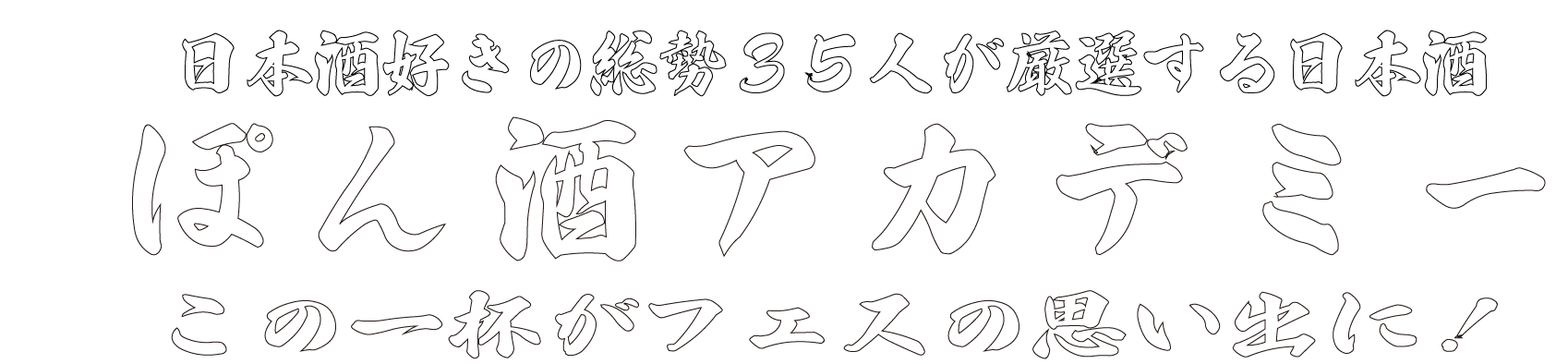



コメント