枡(マス)とは
枡(升とも書く)は穀類、液体、粉などの量を計る容器。
現在ではマスと言えば一升枡(イッショウマス)を指す。
1升は液体で1.8リットㇽで、昔は一升枡によって年貢が計られたほか、売買、交換、賃借などの経済行為における重要な計量具であると同時に、日常の生活道具として主に台所で使われた。
桝の形状
木製で方形(箱型)が一般的で、統一的な企画は、大宝元年(701年)編纂の大宝律令に、大升と小升の制、1升が10合、10升が1斗、10斗が1石(こく)に定められた。
その後、雑多な枡が併用された時期を経て、豊臣秀吉の時代の太閤検地に10合1升の京枡が使われ、これを受けて徳川幕府も京都と江戸に枡座を設けて企画を管理した。現在の枡は京枡に準じたものである。家庭の米櫃に用いるのは5勺(1合の2分の1)枡、祝義などの枡酒用はふつう一合枡が使われる。
迷子の魂を呼び戻す
米や酒などを計り分ける道具である枡は、その計量と分配の機能が神の役割うぃ代行するものと考えられた。
神の恵みである大事な食物が、枡で適正に計量、分配される行為の背景に、人々は公明正大な神の力を感じていたのである。
例えば、節分の豆撒きに用いられる枡は、単なる豆を入れるための容器ではない。神聖な穀物である豆に鬼や病魔退散の霊力を宿らせるために、神霊を降臨させる呪物としての意味を持っている。
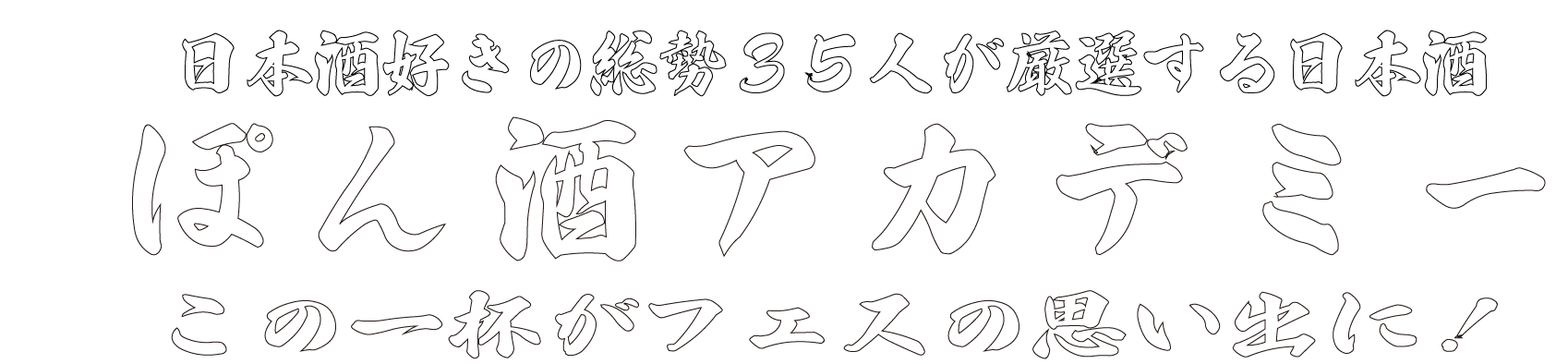

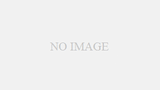

コメント